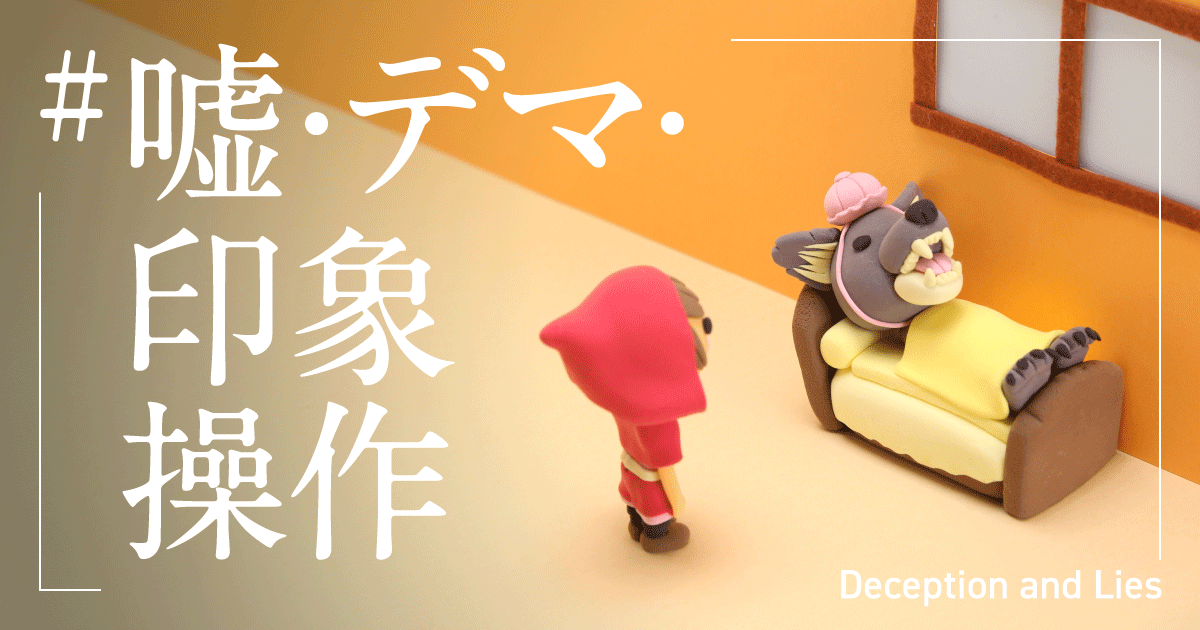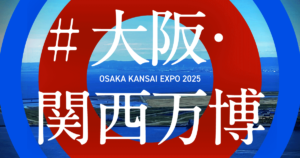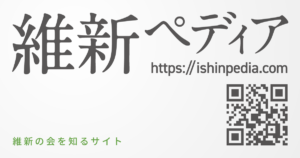兵庫県政混乱が続く中、知事のパワハラ告発者の個人情報が漏洩した問題で立ち上げられたという調査委員会の不透明さが問題視されている。だが、維新に第三者性がないのは、実は今に始まったことではない。維新の公式ファクトチェッカーというX(当時はTwitter)アカウントをご存知だろうか。ファクトチェックの定義をまるで無視した維新の行いは以前から「通常運転」だったといえる。前置きは長くなるが、維新の不透明さのブロセスについて記録しておきたい。
2024年11月17日の兵庫県知事選挙。斎藤元彦氏が再選を決めたが、彼の当選は兵庫県政の混乱が続くことを意味する上、県政正常化を阻むのではという強い懸念が言われていた。それを証明するように、斎藤知事のパワハラ告発者の個人情報の漏洩問題など、県政正常化は遅々として進まない。毎日新聞2025年2月13日記事より引用する。
兵庫県の斎藤元彦知事のパワーハラスメントなどの疑惑が文書で告発された問題で、告発者の私的情報が漏えいした可能性があるとして県が設置した二つの「第三者委員会」の透明性に疑問符が付いている。一部県議が「日本弁護士連合会(日弁連)のガイドラインに基づく第三者委でなく、議会への報告義務もない」と指摘。斎藤氏は13日の記者会見で、調査組織の構成などは明かさず「調査結果が出た段階で、出せるものを出したい」と述べた。
文書告発問題を巡って県は現在、三つの「第三者委」を設けている。一つは2024年9月に設置され、告発文が指摘したパワハラなど七つの疑惑と公益通報者保護の妥当性を調査している。弁護士3人で構成し3月末が報告の期限だ。設置に際し、県議も入った準備委の了承を得て外部委託した。初会合後、委員長の藤本久俊弁護士は「報告書を提出すれば記者会見で説明したい」と明言した。
対照的に、告発者である元県西播磨県民局長の私的情報が漏えいした疑惑に関する二つの調査組織について、県は設置要綱や委員数すら明らかにしていない。
うち一つは、元総務部長が元局長の私的情報を複数の県議らに漏らしたとされる疑惑が調査対象。斎藤氏が24年8月に外部の弁護士による調査を進めていることを明らかにした。県議会調査特別委員会(百条委)で、元総務部長は「守秘義務違反の嫌疑を受ける可能性がある」として証言を拒否。一方、県議2人は元総務部長から聞いたり、見せられたりしたと証言した。担当する県人事課は「漏えいが事実なら懲戒処分の対象。客観性と中立性を担保するため外部に委託した」と説明する。
もう一つは、政治団体「NHKから国民を守る党」の立花孝志党首が24年11月、元局長の私的情報のデータだとして、動画サイトやX(ツイッター)で画像などを公開したケースを調査。県弁護士会に人選を依頼して1月に設置したとされるが、詳細は明らかにされていない。担当の県法務文書課は「調査内容を公表すれば(漏えいした人物の)懲戒処分の調査に支障が出る」としている。
情報漏えいに関する二つの調査について、斎藤氏は13日の会見で年度内に結論を得る見通しを示した。一方、「委員会ということは(委員は)複数いるのか」との問いに対して「会だと複数いるんじゃないですか」などとあいまいな答えに終始した。
自民党のある県議は「この異常事態に『調査を待つ』とリーダーシップを発揮しなくていいのか」と知事の姿勢に疑問を呈し、議会として元総務部長らを地方公務員法(守秘義務)違反容疑で刑事告発すべきだと主張する。
◇「ガイドラインに沿う形での公表前提に」 同志社大の真山達志教授(行政学)は「『結果が出た段階で出せるものを出す』ということでは信頼を失う。少なくとも日弁連のガイドラインに沿う形での公表を前提とすべきだ」と指摘。その上で「公表範囲を県が決めるなら、内部調査と変わらない。ガイドラインに『ステークホルダー(利害関係者)に対する説明責任を果たす目的で設置する』とあり、県にとってそれは県民だろう。個人情報保護などは必要だが、詳細を明かさない理由にはならない」と話している。【中尾卓英、山田麻未、栗田亨】
自分自身のパワハラ等を告発された時には、絶対に厳禁といわれる「告発者探し」に乗り出し、告発を「嘘八百」扱いをした斎藤知事。これは公益通報の専門家からも厳しい指摘を受けた。「兵庫県の対応で特にひどかったのは、公益通報者の探索をおこなわせ、その探索の過程で押収したパソコンから、公益通報者のプライベートな内容の文書を把握し、結果として、公益通報者を黙らせようとその情報が使われたとみられることです」(上智大学教授 奥山俊宏氏)。
今回の情報漏洩問題は斎藤知事にとって問題解明が不都合でもあるのか、会見で何度問われても、積極的にそこに取り組む姿勢は見られなかった。この第三者調査委員会、年度内には何らかの結論を出すとのことだが、いずれにしても第三者性に乏しく、本当にまともに取り組まれているのか、疑問の声が上がっている。
さて、前置きが長くなり過ぎたが、維新の「第三者性」の乏しさは、今に始まったものではないことを記録しておきたいと思う。維新の公式「ファクトチェッカー」というXアカウントがある。2021年2月18日
これは当時、批判が起き、報道もされた。朝日新聞2021年2月27日の配信記事より引用する。

地域政党・大阪市維新の会は、ツイッター上で「ファクトチェック」の第一弾を投稿した。大阪市の新型コロナウイルス対応を批判するツイートに関する内容だ。市長を出し、市議会与党の維新が「ファクトチェック」をすることには、「非党派性」の原則から逸脱し、第三者による検証ではないとの批判が出ている。維新の投稿は26日夜。新型コロナ感染者の濃厚接触者だとする人が「(自宅療養期間中に)大阪市の保健所からはついに一度も連絡無し」「まさに放置状態」などと2月12日に書き込んだツイートに対するものだった。アカウント名が分かる形で引用して「感染者数の爆発的増加に伴い、(療養期間中に保健所が)積極的に健康状態を聞き取る方式から、ご本人が異変を感じた際に申し出て頂く受動型に切り替えている」とした。
維新代表・吉村洋文 大阪府知事は27日、朝日新聞などの取材に「維新として正確な情報を発信するのが不安の解消にもなる。個人攻撃をしているわけではない。言論に対しては言論で対抗するのがあるべき姿だ」と述べた。
日本でファクトチェックを推進するNPO法人「ファクトチェック・イニシアティブ」によると、ファクトチェックには「非党派性・公正性」など国際的な五つの原則がある。楊井人文事務局長は「政党として情報発信や言説に反論する自由はある」とした上で、「大阪維新の会は政治団体であり、非党派性・公正性の原則から外れる」と指摘。さらに「ツイートの内容が事実かどうかをレーティング(真偽の判定)せず、あたかも誤情報だという印象を与えている」と問題視する。
ネット上では、今回の維新の動きについて「自己を正当化することがファクトチェックなのか?」「『ファクトチェック』ではなく『吊(つる)し上げ』」「脅迫もしくは弾圧だ」「公党が個人のツイートをさらして、個人攻撃か」といった批判が相次ぐ。維新内部からも「与党の維新がいろいろ言われるのは当然。ファクトチェックをする立場ではない。政党として未熟で、おごりがある」(市議)との声が出ている。
当時、リテラでもこの件を取り上げている。吉村洋文氏は「“維新憎し”のデマに個別に僕自身が反論するのも大変なので、大阪維新の会として対応しようと。そのための組織を内部で立ち上げて、誰とは言わないがファクトチェックを担当する議員を置いて、その議員の方で事実をファクトチェックのアカウントから発信していきたい」とコメント。
しかし、「維新憎し」どころか、事実しか書いていない市民のツイートを晒した上に、苦しい言い訳をして責任回避をする内容でしかなかったことは本当に残念だ。維新ペディアではまともな発信をした市民のアカウントやその投稿内容を晒す気にはなれないので控えるが、リテラの記事に詳しいので、ご覧いただければと思う。

さて、現在このアカウントは動いていない。第8弾まで市民らのツイートを晒したが、その都度批判が巻き起こり、「何を言ってもブーメラン」となり、「それなら維新のこの問題をファクトチェックしてください」などというリプが溢れ、「まさに大喜利」という状態になった。維新としても動きにくくなったのだろうと推測される。
だが、維新ペディアはこの悪質さを忘れず記録しておく。今回の兵庫県の第三者調査委員会が、日弁連のガイドラインに基づいたものですらないように、公党である大阪市維新の会が市民らの批判を「維新憎しのデマ」と決めつけ、まともな説明責任を果たすどころか、報復のようにアカウントを晒す行為はまさに恫喝としか呼びようがない。
最後に「リテラ」が紹介した、当時のSNS上のツッコミを記しておこう。
〈まず自分たちへのチェックをせんとな〉
〈昨年春頃、吉村知事が言われていた「コロナの弱点見えてきた」について調査を〉
〈大阪市廃止の住民投票なのに大阪市はなくなりませんと喧伝されていたファクトチェックお願いします〉
〈イソジンと愛知県のリコールについてお願いいたします〉
〈イソジンのファクトチェックを第一にお願いします。その次はカッパのファクトチェックをお願いします〉